この記事は1年前のオンラインサロン西野亮廣エンタメ研究所の過去記事です。
2018年8月10日
【『おもしろい』を売る】
新しく何かを仕掛けた時は、「これは、こうで、こうで、こうだから上手くいかない」と言って、新しいものを否定することでドヤる層(それでしか自分の存在を証明できないブス)が必ず一定数いる。
もちろん、否定すること自体は悪いことでも何でもないと思うんだけど(僕もしているので)、その切れ味があまりにもブサイクな場合があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『しるし書店』の場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「『しるし書店』がいかに売上が上がらないか?」というツイートが回ってきまして、その分析というのが
「手数料が○○%だから、これでサービスを回す為には、月に最低でも○○冊は売らないといけなくて、現実問題、それでは売上が出ない」
といったもので……口が悪くなってしまったらゴメンナサイなんだけど……
一体どの昆虫に育てられて、
どのビタミンを接種し続けたら、
その金魚サイズの脳ミソに仕上がるのかを質問したいです。
『しるし書店』の本質が、まったく見えてないんだよね。
脳ミソが金魚サイズだから、『しるし書店』の売上が「手数料」でしか発生していないと思っている。
そんなわけがない。
手数料でしか売上が出ないのであれば、こんなサービスはとっくに辞めてる。
アホすぎてムカつくから、おもくそ生々しい話をするけど、『しるし書店』の売上がどこで出ているかと言うと、『オンラインサロン』と『講演会』の二つ。
『しるし書店』をやることで、その裏側を知りたいオンラインサロンメンバーが増えるし、講演会で「信用経済」について語る時には、必ず「しるし書店」の話をしている。
「1500円」の本が「3万円」で売れている事実は、「信用経済」を説明する上での例としてキャッチーなんだよね。
つまり、オンラインサロンの売上や、講演会の売上の中に、『しるし書店』の売上が入っているんだよね。
ついでに言っちゃうと、「現代のお金」について語っている僕の書籍の印税の中にも。
逆に言うと、オンラインサロンメンバーが増えなかったり、講演会や書籍で喋れなくなってしまった時が、『しるし書店』の潮時だよね。
すべては、「面白いか、面白くないか」で、「面白い」かぎりは、その背景や物語を販売することで、売上は出る。
手数料なんて、まったくアテにしていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『貸し会議室』はレンタル料でまわす?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もう皆さんの中で答えは出ていると思うけど、今度、五反田に作ろうとしているサロンメンバー限定(予定)の『貸し会議室』なんて、レンタル料で回そうなんて1ミリも考えちゃいない。
内装(世界観)をゴリゴリに作り込むとなると、レンタル料で回るわけがない。
それでいい。
毎月、赤字でまったく問題ない。
大切なのは、サロンメンバーの皆さんに「このサロンは“面白い”なぁ」と思ってもらうことで、思ってもらえれば回収できる。
今、開発しているオンラインギャラリー『プペル』(僕の絵本にまつわる作品だけが出品されるギャラリー)にしたって同じ。
つまるところ、『しるし書店』にしたって、『貸し会議室』にしたって、『オンラインギャラリー・プペル』にしたって、「面白い」と思ってもらう為の『広告』だよね。
「広告費を払って、サロンメンバーを増やしている」という流れ。
『しるし書店』やら何やらがあるから、「次は何を仕掛けるんだ?」に繋がるわけじゃん。
どこからエネルギーを集めて、そのエネルギーをどこに流して、どこでお金が発生しているかをキチンと見極めないと、エンタメで突き抜けることなんて無理。
僕が仕掛ける一つのアクションだけを取り上げて売上ウンヌンの角度から突っ込むのは、
「ホームレス小谷は1日を50円で売っているから、生きていけない」
「Googleは無料でサービスを提供しているから、儲からない」
と言っているようなもので、そんなバカにはならないで。
ちなみに、僕の絵本を一冊作るのには、1000万~2000万円かかります。
印税で返そうと思っているわけねーじゃん。

西野亮廣エンタメ研究所の入会ページのリンクはこちら

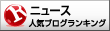

コメント